現場主導で離職率を下げる―医療職の「定着」を叶える3つの職場改善策
- 定着する医療現場のつくり方
- 2025年4月11日
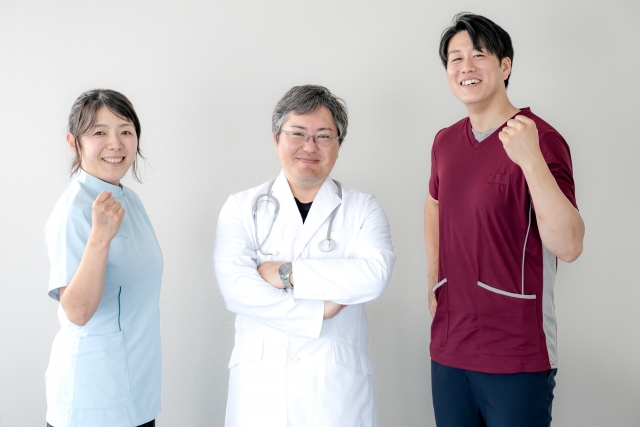
医療機関で働く看護師や診療放射線技師、臨床検査技師といった専門職の離職理由は、給与や待遇よりも「人間関係」や「職場の雰囲気」にあることが多い。本記事では、実際に定着率が向上した医療現場の取り組みから、「現場主導の定着施策」「チームの心理的安全性向上」「新人育成と既存職員の役割設計」の3つのポイントを紹介する。医療現場で「辞めない職場」を目指す求職者に向け、リアルな職場改善の実例を交えて、職場選びの視点を提示する内容となっている。
医療職が職場を去る本当の理由とは?
医療現場では慢性的な人手不足が続いており、とくに看護師や診療放射線技師、臨床検査技師といった医療職種の離職が深刻になっています。
離職理由として多く挙がるのは、給与や待遇よりも「人間関係」「育成体制」「職場の雰囲気」といった職場環境に関するものです。
厚生労働省の「医療施設調査(2022年)」によると、病院勤務者のおよそ20%が5年以内に職場を離れており、定着率の向上は医療機関にとって重要な経営課題となっています。
本記事では、求職者の視点から「定着しやすい職場とは何か」を見極めるポイントを整理し、現場主導で実施できる改善策とその具体的な効果について紹介していきます。
実際、多くの医療職が退職を決める背景には、心理的なストレスがあります。とくに新人や若手が離職しやすい職場には、以下のような課題が見られます。
- ・指導体制が曖昧で、孤立しやすい
- ・業務分担に偏りがあり、負担が集中する
- ・パワハラや無意識の攻撃的言動が存在する
こうした問題は、経営層には見えにくいため、現場での気づきと対応が定着率に大きく影響します。
現場主導の取り組みが定着率を変える
定着率を改善するためには、「上からの施策」よりも「現場スタッフが主体となった改善活動」のほうが効果的です。
ある中規模病院では、以下のような取り組みにより離職率を3割以上改善しました。
- ・毎月、現場スタッフによる業務カンファレンスを実施
- ・新人向けに「同行OJTシート」を導入し、振り返りを習慣化
- ・ベテラン職員が若手のメンター役として機能する体制を構築
このような取り組みは、スタッフ間の信頼関係を育てるだけでなく、「自分たちで職場を良くしていく」という意識を生み、職員の定着意欲につながります。
心理的安全性が職場文化を変える
心理的安全性とは、誰もが安心して発言でき、否定や非難を恐れずに意見を交わせる職場環境のことを指します。
Googleが社内で行った「プロジェクト・アリストテレス」でも、チームの成果にもっとも影響を与える要素として心理的安全性が挙げられています。
医療現場でも、以下のような工夫によりこの環境づくりが進められています。
- ・フィードバック面談を「相談の場」として位置づける
- ・小さな失敗を共有できる「振り返りの時間」を設ける
- ・上司が「質問や提案を歓迎する姿勢」を積極的に示す
こうした取り組みは、新人職員の安心感にもつながり、結果的に早期離職の防止につながります。
とくに、新卒や第二新卒の職員にとって「相談しやすいかどうか」は職場選びの大きな基準のひとつです。
新人とベテランの関係構築がカギ
職場における教育制度の整備以上に、新人と既存職員との信頼関係づくりが重要です。
教育が属人的な職場では、指導する人によって対応が異なり、新人が混乱や不安を感じることが多くなります。
効果的な取り組みとしては、以下のようなものがあります。
- ・指導担当者を定期的に交代するローテーション制の導入
- ・毎月の育成レポートの共有とフィードバックの実施
- ・新人担当者と職場リーダーの役割を分けて明確化
これにより、新人が「誰に相談すればいいか」がわかりやすくなり、不安や孤立を感じることが少なくなります。 初期段階での丁寧なフォローが、離職を防ぐ大きなポイントです。
求職者が選ぶべき「定着する職場」の見極め方
求職者が「定着しやすい職場」を選ぶためには、以下のようなポイントに注目することが大切です。
- ・教育体制がきちんと文書化されている
- ・年齢構成のバランスが良く、偏りがない
- ・面接時に職場見学ができ、雰囲気を確認できる
- ・離職率や定着率が公開されている
- ・チームの役割や業務分担が明確にされている
これらの情報は、求人票からは読み取れないことも多いため、見学や面接時にしっかり確認することが重要です。
職場の空気感やスタッフ間のやりとりなど、実際に足を運ぶことで見えてくる部分も多くあります。
まとめ
医療職の離職は待遇以上に職場環境や人間関係によって左右されることが多く、現場主導の改善が定着率向上のカギとなります。
心理的安全性の確保、新人育成体制の整備、信頼関係の構築といった実践的な取り組みによって、働き続けやすい環境づくりが可能になります。
求職者にとっても、定着しやすい職場の見極めは重要なテーマです。
職場選びの参考として、実際の制度や現場の姿勢を確認しながら、自身に合った職場を見つけていくことが求められます。